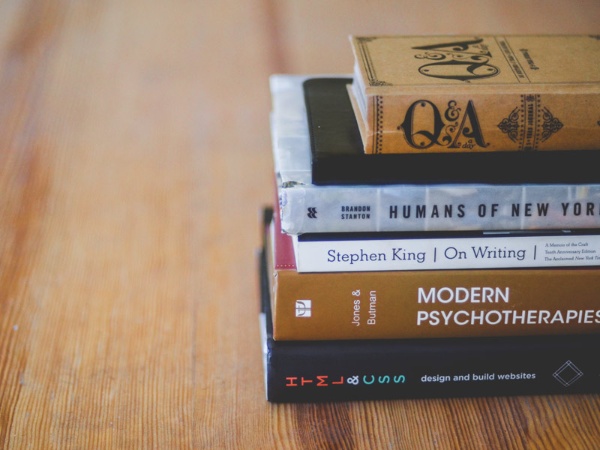アオイ電子は半導体を最終製品に仕上げる「後工程」の受託製造で国内トップシェアを誇る。積極的にM&A(合併・買収)を進めて対応領域を拡大し、ワンストップですべてを請け負えることが強みだ。半導体不況の中でも、新たな挑戦を続ける同社の成長の経緯と経営戦略について木下和洋社長に聞いた。
アオイ電子は、半導体を最終製品に仕上げる「後工程」の受託製造を主軸とする。シリコンウエハーをチップの形に切り分け、基板の上に固定して配線。正常に動くかを検査し、その先の梱包(テーピング)までワンストップで請け負うのが強みだ。日常生活に欠かせないスマートフォンやコンピューターをはじめ、家電・情報通信、産業用設備、自動車などの各メーカーに広く部品を供給している。
大手企業の系列に属さない独立系メーカーで、取引先は国内外の多岐にわたる。「後工程」を請け負う企業(OSAT・オーサット)としては日本では唯一、世界トップ20に入る。
そんなアオイ電子の成長を支えてきたのは、同社ならではの「提案力」だ。技術と営業の両方の知見を兼ね備えたセールスエンジニアたちが、顧客が次に作ろうとしている製品や必要な部品を先読みし、新たな提案を続けることで信頼を得てきた。社内には創業時から生産設備の開発チームがあり、顧客ニーズに素早く対応する。独自性のある部品を、小ロットかつ短期間で生産できるのが強みだ。
半導体領域の他にも、あらゆる画像出力機器の心臓部に用いられるサーマルプリントヘッドや各種センサーなど、機能部品の製造も請け負っている。2022年に就任した3代目の木下和洋社長は、「受託生産なので、とにかくお客様とのフェイス・トゥ・フェイスのやりとりが大切。細かくニーズを聞き、戦略的に提案し続けることが欠かせない」と話す。
小型化の波に乗り成長

アオイ電子は1969年、大手電子部品メーカーの協力工場として大西通義(みちよし)氏が創業した。80年代後半には大手メーカーとの資本提携を解消して独立。バブル崩壊のあおりも受け、独立後しばらくは「首の皮一枚というような厳しい状況が続いた」(木下社長)という。
が、90年代に入ると、電子製品の小型化に伴って、半導体も軽薄短小のニーズが増加。アオイ電子はいち早く小型半導体に注力して勢いに乗り、2000年には東京証券取引所第2部(現在はスタンダード)に株式上場を果たした。
「半導体は讃岐うどんに似ている」──。2年前に亡くなった大西氏は生前、社員にそう語っていたという。どの店のうどんも原料は小麦粉だが、職人の腕1つで味が変わる。同様に、半導体も製造元は複数あるが、技術を磨けば企業の価値を高められるとの意味だ。

それゆえ、00年代以降に多くの国内メーカーが安価な労働力を求めて生産拠点を海外に移す中でも、同社は地元香川での製造にこだわった。「香川県出身の社員に支えられてきた企業であり、顧客の多くは県外なのもあって、『外貨』を稼ぐことで地元に貢献したいという思いがあった」(木下社長)という。
大西氏の引退後は非創業家のプロパー社員が経営を引き継いだ。3代目の木下社長は1980年にアオイ電子に入社。社長就任前は管理部門が長く、「自分は技術に関しては素人。だからこそ社員の意見をまっさらな状態で聞き、信用することができる」と前向きだ。
【春割・2カ月無料】お申し込みで…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号13年分のバックナンバーが読み放題